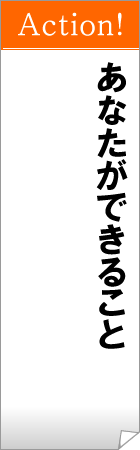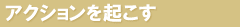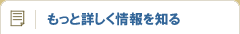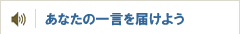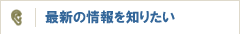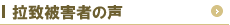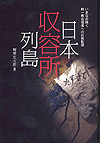冊子・ビラ・書籍
強制改宗をくつがえす統一神学
聖書の権威を否定しているという批判
統一教会の『原理講論』は、聖書は神の永遠の真理それ自体ではなく「真理を教示してくれる一つの教科書」なので、聖書を「不動のものとして絶対視してはならない」と述べている (30頁)。それゆえ、特に福音派は、統一教会は聖書の権威を否定し聖書を冒涜している、と批判する。しかし、聖書の権威といっても様々な見解があるのが事実であり、福音派の見解のみが正しいという保障はどこにも無い。統一教会の見解は聖書の権威を立派に認めているし、その見解は多くのキリスト教徒の見解と共通している。かえって福音派の見解の方に大きな問題がある、と指摘するキリスト教徒は多い。
福音派は聖書の「逐語十全霊感」(verbal plenary inspiration) を信じる。これは神の霊感の程度を示す「逐語霊感」(verbal inspiration) とその範囲を表す「十全霊感」(plenary inspiration) を合わせたものである。これによれば、聖書はその思想内容の程度に止まらず一字一句の表現までも神の霊感によって書かれたものであり (逐語霊感) 、また聖書の範囲のある部分だけではなく聖書全体が神の霊感によるものである (十全霊感) という。だから聖書の写本や訳本は別としても、元々の聖書記者たちによる原典全体にわたって、科学や歴史に関する記述をも含めて、その一字一句の文字の表現に誤りが無いはずであり、そういう意味で聖書は「無誤性」(inerrancy) を持つという。それゆえ、聖書は神の永遠の真理それ自体であり、絶対的権威を持つという。
しかし、キリスト教におけるもう一つの代表的な見解は、福音派の見解とは違い、「内容」としての神の真理とそれを「表現」する聖書の文字を一応区別し、聖書の権威は「表現」としての文字それ自体にあるのではなく「内容」たる神の永遠の真理にあるとする。この「内容」と「表現」の区別は分離、隔離ではなく、二者一体の中における区別である。この区別は、神 (セオスθεός) という「内容」を我々の言葉 (ロゴスλόγος) で「表現」したものが「神学」(セオロギアθεολογία) であるというギリシャ語の「神学」の定義の中の二者の区別にも見られるように、キリスト教神学では常識中の常識である。聖書は神学的だといえることや、聖書神学という分野が存在することからして、聖書にもこのような神学の定義が当てはまるのは当然のことであろう。だから聖書が神の霊感によるものであっても、その文字の「表現」は人間が係わっているので完全ではないはずであり、特に科学や歴史に関しては間違いがあるかもしれない。でも、文字の背後にある神の真理とか信仰の「内容」には誤謬が無いはずなので、それを「無謬性」(infallibility) と呼び、福音派のいう文字の「無誤性」(inerrancy) とは違った意味を持たせる。これによれば、聖書の権威はまさにこの「内容」としての神の真理の「無謬性」にあるのであり、福音派のいう聖書の文字の「無誤性」にあるのではないという。
同じように統一教会の『原理講論』も、聖書が神の真理を教示する一つの教科書であるという時、「表現」としての教科書の背後にある「内容」としての神の真理は「唯一であり、永遠不変にして、絶対的なもの」(30頁) であるとみなし、神の真理自体の「無謬性」をはっきりと認めていることに注目されたい。統一教会は聖書の権威をここに見いだす。だから文鮮明師も特に若かりし時に、聖書の紙が擦り切れてボロボロになるほど真剣に読まれた。背後の無謬なる神の真理を把握することによって人間の諸問題を解決するためであった。多くの信仰的なキリスト教徒と同様に統一教会は、聖書は福音派のいう「逐語十全霊感」や文字の「無誤性」によるものでなくても、やはり神の真理の書として神の霊感の下に書かれているので、聖書を読む時に聖霊の力を受けて読めば、文字の表現の背後にある神の永遠の真理を受けることができる、と信じる。だから、福音派は福音派以外の信仰者を一緒くたにリベラル派呼ばわりをしてはならない。
聖書が神の霊感によるものであるということは、聖書自体もそういっているので、キリスト教の歴史の出発点より受け入れられて来た。しかし、福音派のいう聖書の文字の「無誤性」の説は初めからあったわけではない。それがキリスト教の中で正式に主張されるようになったのは、18世紀の啓蒙主義に対する反作用として福音派が出現して、特に「逐語霊感」が以前より強調されてからのことである。特に20世紀になってアメリカの福音派の中でそれが盛んに強調され、1978年には「聖書の無誤性に関するシカゴ声明」(The Chicago Statement on Biblical Inerrancy) が発表された。勿論、16世紀の宗教改革はカトリック教会の権威に反対して聖書の福音を重んじたので福音的であったとはいえるが、今の福音派のように聖書の文字の「無誤性」を説いたわけではない。宗教改革の基本原理である「聖書のみ」(sola scriptura)、 というのは「形式原理」として聖書の重要性を訴えているだけであり、その文字をそのまま神の真理として絶対的に受け入れよ、というのではない。むしろ聖書の中にある「内容原理」である神への信仰を受け入れよ、というのである。20世紀の「新正統主義」を代表する偉大な神学者カール・バルト (Karl Barth) も、聖書のウルクンデ (Urkunde 文書) の背後にある神というザッヘ (Sache 事柄) を受け入れることの重要性を説いた。
福音派の聖書観には少なくとも二つの大きな弱みがある。一つは、その「逐語十全霊感」の説が、聖書全体の一字一句が神の霊感によって書かれたと説くので、神の口述を聖書記者がワープロかロボットのように機械的に筆記したという悪名高い「口述筆記説」(dictation theory) と同じに見えることである。「口述筆記説」はファンダメンタリスト(根本主義者)だったら受け入れる者がいるかもしれないが、福音派はやはりそのような説を奉じているとは見られたくないので、ある程度、聖書記者の参加を神の霊感とのダイナミックな関係でとらえる「動力霊感」(dynamic inspiration) なるものを考える。これによると、神はその霊感で以って、聖書記者の持つ個性、語彙、文法の知識などの枠組みから一番適切な言葉を選んで、聖書の一字一句を構成して行くというのである。しかしこれでは、聖書記者が人間として初めから持っている不完全な枠組みが土台になっていることになり、結局は、元々の文字の「無誤性」を捨てるような矛盾に突き当たるのではなかろうか。
福音派の二つ目の弱みは、聖書の文字の「無誤性」が偶像崇拝的な立場を持つということである。この「無誤性」は、聖書の文字をそのまま永遠、不変、絶対の神の真理と見なし、神でないものを神としてしまうからである。だから、有名なエミール・ブルンナー (Emil Brunner) を初め他の多くの信仰的なキリスト教徒は、福音派が聖書を「紙の教皇」のように偶像崇拝している、と批判した。この批判をかわすために、福音派は「無誤性」といっても「絶対無誤性」(absolute inerrancy) ではなく「十全無誤性」(full inerrancy) の方を奉じているから大丈夫だという。ファンダメンタリストが信じるような「絶対無誤性」の立場は、歴史や科学についての記述も現代人の尺度からして絶対に正確であると説く。一方、福音派の「十全無誤性」の立場は、歴史と科学についての記述は現代人から見ると必ずしも正確 (exact) ではないが、当時の聖書記者たちからすれば完全に真実 (fully true) であり無誤 (fully inerrant) だったはずなので、いずれは正確でない部分の説明がつくという。しかし、このような批判のかわし方は、結局、「表現」としての聖書の文字がやはりある意味で不完全だと認めることになり、再び「無誤性」を捨てざるを得ない矛盾に突き当たるのではなかろうか。
目次