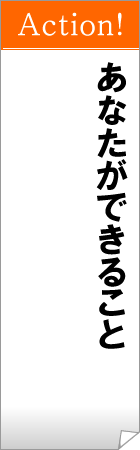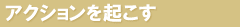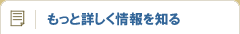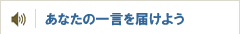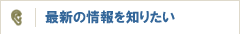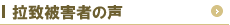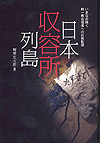有識者の声
山田茂論文『いまどきのカルト観を問う』
社会学者 ペンネーム:山田茂
はじめに
近年,日本の大学界の学生生活指導分野で「カルト」という言葉を使った広報活動が行われている。この言葉をめぐっては,欧米ではその使用法に問題が多いとの見解が提起されてほとんど使われない流れの中にあるが,日本では学術的なレベルを逸脱して恣意的な形でこの言葉を使用している事例が多い。そこで「カルト」についての学術的知見を整理しながら,この言葉を使うことの目的と問題点を指摘する。
カルトと言えば,常に次のようなエピソードが思い起こされる。
多少筆者の加筆もあるが,彼らこそ初代キリスト教徒,つまりクリスチャンであった。ローマ帝国は,キリスト教を迫害する際,このような考えつく限りの悪態をついていたのである。現代風に言えば,カルトとして激しい批判に晒されていたのであった。しかし今や,世界宗教となったキリスト教へのこうした非難は行われない。
オウム真理教事件(1995年が中心)から火がついたいわゆる「カルト問題」について,15年を経て世間の人々の関心は下火になったが,一部ではいまだにこの問題を糧にする人々もいる。改めて「カルト問題」を考えてみたい。
ドイツの社会学者マックス・ウェーバー(Max Weber,1864-1920)と同国神学者のエルンスト・トレルチ(Ernst Troeltsch,1865-1923)による「チャーチ=セクト類型」(church-sect typology)によると,「カルト」(=セクト:独語Sekte)とは宗教団体の初期形態のことである。宗教団体はセクトである段階において,周辺からの迫害に遭い,悪宣伝にさらされる。しかし,市民権を得るにしたがってその悪宣伝はなりを潜め,次第に正式な社会集団(=教会)として認められるようになる。したがって,セクト(カルト)とは,まだ市民権を得ていない宗教団体ということである。
本稿の結論を先に示せば,現在,カルト団体として世間的な批判が行われる場合,それは批判する当事者にとって不都合な団体にそのレッテルを貼り,悪宣伝の対象にしている面が強いということである。
そこでは,カルトの定義についての客観的な指標がなく,それが恣意的に行われている。したがってカルトとの批判が展開される場合,その批判を行う主体の意図が何であるかに注目して事態を分析する必要があるだろう。
但し,オウム真理教のように殺人を是とした教団に関しては,この例外であること予め断っておく。たとえば,“相手がこの世で罪を犯すことを容認するより,あの世に送ってあげ,この世で罪を犯すことを予防してあげたほうがその人のためになる”との理屈(ポアの思想)による殺人は,とうてい神仏の御心とは言えない。目的のためには人殺しという手段を選んでもよいという手法は,すでに3300年前の紀元前13世紀のモーセの十戒(「汝,殺すなかれ」)において否定されている。
1.カルトの宗教社会学的意味
アメリカの宗教社会学者デイヴィッド・モバーグ(David O. Moberg,1922- )による「教団のライフサイクル論」によってもう少し詳細なカルトの理解を試みよう。
デイヴィッド・モバーグは1922年アメリカのミネソタで生まれた。シアトル・パシフィック大学を卒業後,修士号をワシントン大学で,博士号はミネソタ大学において1952年に取得している。
ミネソタのべテル大学で20年間教えた後,ミルウォーキのマーケット大学(Marquette Univ.)の社会学教授として1991年の退官まで教鞭をとった。その間,米国宗教社会学会の会長を1977年に,米国宗教研究協会会長を1982年にそれぞれ務めた。
日本におけるモバーグの研究者である森岡清美の『新宗教運動の展開過程』(創文社1989年)によると教団のライフサイクルは次の5段階を経るという。
| 段階 | 状態 | 内容 |
|---|---|---|
| 第一段階 | 萌芽的組織 | 社会不安を背景としてカリスマ的・権威主義的・預言者的リーダーが登場すると,彼をめぐって集団興奮が起こり,カルト(cult)ないしセクト(sect)が出現する。 |
| 第二段階 | 公式的組織 | 扇動的なリーダーシップは次第に影をひそめ,目標が成文化され,部外者との差異が強調される。 |
| 第三段階 | 最大能率段階 | 公式的構造が発達し合理的組織がカリスマ的リーダーシップにとって代わる。役職者は熱心に効率よく義務を遂行し,礼拝の儀式や管理の手続きは目的ではなく手段であることがわきまえられている。若さと活力にあふれた生命力が最大の段階。軽蔑されたセクトの地位から世間の承認を得たデノミネーション(教派:denomination)の地位に移り,部外者への敵意は消える。 |
| 第四段階 | 制度的段階 | 確立した官僚制が自分たちの特権の保持に関心を持ち,信徒の僕でなく多くの要求をする主人となる。礼拝は空しい儀式となり,宗教的象徴は個人の内面的帰依を伴わず,形式主義が集団の生命力を掘り崩す。外界との葛藤はまったく去って社会の習律への同調が徹底し,会員資格の標準が緩む。 |
| 第五段階 | 解体段階 | 腐敗がはびこり官僚制機構が会員のニーズに対応しないため,退会が相次ぎ留まる者も本気で教えに従うことはない。一部のリーダーや会員が信仰復興の改革運動(再生運動)を起こして生命力が回復された場合には新たしいサイクルが始まるが,そうでなければ教団は解体に向かう。 |
(同著11-12頁より作成)
モバーグもウェーバーらの伝統を継ぎ,草創期の教団の形態をカルトあるいはセクトとしている。それを集団的興奮と定義しているところは,教団初期の熱狂的雰囲気をよく伝える用語といえるのではないだろうか。
次第に制度化されるカルトやセクトは,そのうち世間からの承認,つまり市民権を得てデノミネーションに転化する。ちなみにDenominationは『大辞林』によるとsectより大きい宗派,教派となるが,宗派は同じ宗教のなかでの分派のことを指す。キリスト教内のプロテスタントであればペンテコステ派とかバプテスト派などである。一方,教派とは一定の教義のもとに組織化されている宗教団体であることから,キリスト教,仏教,ユダヤ教,イスラム教などの教団を指す。
いずれにせよモバーグによると,セクトやカルトは教団のライフサイクル論の第三段階において,世間からの非難を受けなくなると推測される。
2.悪意的カルト用語の出現
さて,宗教社会学的にはカルトやセクトに対する悪意はあまり感じられない。むしろ,ウェーバーにいたっては,特にキリスト教などを世界を変革することになる「歴史の転轍手」との位置付けも行っているほど好意的であった。
そのセクトをカルトと再定義したのが,アメリカの社会学者のハワード・ベッカー(Howard Saul Becker:1928- )であった。ベッカーはシカゴで生まれた後,シカゴ大学を卒業,博士号もシカゴ大学で取得した。主にノースウェスタン大学にて教鞭を取った。
その間アメリカ社会問題学会会長も務め(1964年),犯罪理論におけるラベリング理論の提唱者としても著名である。社会的に排除される傾向のある集団への関心をベッカーが持ったのは,プロのジャズピアニストという変わった一面を持っていたことと関係があるのかもしれない。
そのベッカーは1950年に非キリスト教的なスタイルを持つ新興団体を,新たな類型としてセクトに含め,これを「カルト」と定義した。ベッカーの言うカルトは心霊術,占星術などの信者集団で,小規模かつ緩やかな組織構成という特徴を持つものであった。
このカルト概念を日本におい反社会的で危険な存在としたのが「破壊的カルト」との用語である。この用語は,スティーブン・ハッサン著『マインド・コントロールの恐怖』(恒友出版1993年)において世間に流布された。
オウム真理教問題に取り組んだ弁護士の滝本太郎はその定義を「教祖または特定の主義,主張に絶対的に服従させるべく,メンバーないしその候補者の思考能力と思考意欲を著しく低下させないし停止させ,目的のためには違法行為も繰り返してする集団」とし,「オウム集団や統一教会がその典型」(全青協HPより)と述べている。
こうしてカルトは今や,カルトとの表現だけでは不十分と思われたのか,一目瞭然の形容詞「破壊的」との冠をかぶせられ,有無を言わさず反社会的な存在であると決めつけられることになった。
3.欧米での異なる見解
(1)フランス「反セクト法」の周辺
しかし,カルトに対する欧米での評価は二つに分かれている。大雑把に分ければ,大陸ヨーロッパにおいては「破壊的カルト」を標榜するグループと似たような見解を持ち,アングロサクソン系の英国や米国ではまったく逆の見解を取る。
先に「破壊的カルト」グループが好んで例に持ち出す,フランスの「反セクト法」から考察してみよう。資料入手が容易なインターネットサイトのWikipedia「反セクト法」からその内容を要約する(Wikipediaの「反セクト法」から抜粋)。
同法の正式名称は「人権及び基本的自由を侵害するセクト的運動の防止及び取締りを強化する2001年6月12日の法律第2001-504号」である。同法では,「セクトと目される団体が繰り返し犯罪を犯した場合,裁判を通じてその団体の強制解散させるかどうかの可否を問えるようにした法律」であるという。
問題はどの団体がセクトかを,誰がどのように決めるのかということになる。その点に関してWikiは「フランス政府の規定による社会との軋轢を生む傾向のある団体」と解説している。同法には団体名はまったく記載されていないが,その点に関してフランス政府は1995年と1999年にリストを公表した。1999年版で取り上げられた日本関連の団体は,崇教真光,世界基督教統一神霊協会,ラエリアン・ムーブメント,サイエントロジー,創価学会,エホバの証人であった。
1995年版ではさらに多くの団体がリストアップされていたものの,それらは諸般の事情から削除された。そのなかにはイエス之御霊教会,幸福の科学,霊友会,神慈秀明会など日本の新宗教と呼ばれる団体のかなりが「セクト指定」されていたのであった。
またフランス「反セクト法」を模倣したベルギー法では,カトリック教会では正式の機関と認定されている「オプス・デイ」までカルト団体に含んでいるとしてバチカンからも批判された。
「オプス・デイ」(Opus Dei:ラテン語で「神の業」の意)とは,通常,世俗(世間)外で独身として禁欲生活を過ごすカトリック聖職者に対し,世俗内で労働に勤しみかつ妻帯する実質上の聖職団体である。映画「ダビンチ・コード」でも歪曲して取り上げられてカルトと誤解されることが加速した「オプス・デイ」は,世界80か国に8万人余の会員を有するという。
この事案からみてもわかる通り,同法の問題点は,セクトの普遍的定義の曖昧さである。当局にとって不都合な団体をセクトと指定すれば,その団体を社会的に葬り去ることが可能になるという点であった。結局,フランス政府はセクトの指定を2005年に廃止した。やはり具体的なセクト指定には無理がある。定義を抽象的なままにしたほうが得策と判断したのだろう。
この点を指摘したのが,鹿児島大学の中島宏教授が『一ツ橋法学』(2002年11月1巻3号)書いた「フランス公法と反セクト法」論文である。参考文献としてWikiに紹介されているところは好感が持てる。
そこでは,「反セクト法」成立の背景について,Wiki論文とはまったく異なった見解を示していることがわかる。中島は「フランス人を最も震え上がらせたのは,1995年の集団目殺事件で16人を焼死せしめた太陽寺院である。この事件は1997年にかけてスイスやカナダでも連鎖的に集団自殺を誘発し,約70人が命を落とした」(935頁)と強調しているのである。Wikiでは「反セクト法」成立の背景には統一教会問題があると指摘していた。
また中島論文で具体的に挙げられているセクト問題とは,イスラム教徒の学校におけるスカーフ着用問題,エホバの証人の輸血拒否問題,アルメニア正教会の宗教社団承認問題である。
それらのケーススタディから中島は,「反セクト法」に関して「セクトは信教の目由の享受者たる宗教から事実上排除されている」(同945頁)と述べ,「国家の安全,民主主義擁護,人命尊重といった理由から,曖昧な定義のもとでの宗教的自由に対する制約を簡単に認めてしまう可能性があるといえるだろう」(同959頁)と論評している。
結局,「反セクト法」は概ね国会議員,マスコミ,世論などの支持を得て成立する。しかし4人の元老議員と4大宗教,外国からの反対表明がなされたという。
議員以外で,反セクト法に明確に反対の意思を示したのは,国内では4大宗教団体と 人権連盟そして渦中のセクトである。そしてむしろ国外からの声が大きかった。まず, アメリカが信教の自由を侵害するとして懸念を表明した。元老院議員セルジュ・ラゴ ーシュの発言によると,法案提出後セクトの信者からの抗議メールが議員宛に送信さ れて来たことや,又,アメリカの政治家がフランスに於ける宗教的自由抑圧の立法に 懸念を表明していたことが明かされている。
さらに,欧州評議会のフランスを除いた各国の左派系議員約50人が,連名で反セク ト法の審議を遅らせるように求める宣言を発表したが,後にフランス代表の抗議によ って撤回した。(950-951頁)
唯一,「反セクト法」制定に反対した元老院議員のカルゲタの見解を中島は取り上げ,「セクトを定義することが不可能であるのにセクトを名指ししてその良心の自由や結社の自由を制限することは許されない。そして,この『解決不可能な問題』を解決しようと試みる反セクト法全体にも,そして対象が不確定である各条文にも悉く反対の意思を示した」(同959頁)と激しく非難したことを紹介している。
また「私法学者ドルスネ=ドリヴェは,反セクト法が魔女狩りを導くものでその有益性は疑わしい」(同973頁)と指摘したことも紹介している。
(2)アングロサクソン系国家英米におけるカルト認識
中島によれば,フランスの「反カルト法」ではもう一つの議題が問題になったという。それは「精神操作罪」を導入するかどうかという点であった(中島論文963頁より)。いわゆるマインド・コントロール論である。
最終的に精神操作罪は導入されないことに落ち着いたものの,同罪導入に積極的な議員もいたという。
“自分の意志によらず,巧妙に他人に心を操作される”マインド・コントロール論に対して,アングロサクソン系の英米では否定的である。やや,肯定的姿勢を見せる大陸ヨーロッパとは好対照となっている。
南山大学の渡辺学は『南山宗教文化研究所報第9 号1999 年』において,アメリカでのマインド・コントロール論事情において次のように述べる。
この問題の第一人者の一人としてマーガレット・シンガーを挙げることができる。 シンガーは「社会心理学的影響の組織的操作」(SMSPI)―マインド・コントロールの 学術的な言い換えと考えられる―の理論を立て,リチャード・オフシェとともに法 廷助言などに長年活躍してきた。1988年まで少なくとも37の裁判で元カルト信者がカ ルト教団を訴える際に助言を行ったとされている。しかしながら,1990年になり,米 国政府は彼らの見解が学会の共通した見解を反映していないという理由で彼らを法廷 助言者から外した。
これはアメリカの学会の対応からすれば当然のことである。なぜなら,彼らの見解 が学会の共通した見解を反映していないという指摘は以前からアメリカ心理学会 (APA)からも科学的宗教研究学会(SSSR)からもなされていたからである。(同87 頁)
ヨーロッパで迫害されたピューリタンによる建国となったアメリカでは,個人の自由意思が他人によって捻じ曲げられるという観念は,とうてい受け入れられないようにみえる。法廷においてもマインド・コントロール論は非学問的であるとして退けられた。
最近,『統一教会-日本宣教の戦略と韓日祝福』(北海道大学出版会,2010年3月)を出版した北海道大学の櫻井義秀もベルギーで開かれた第25回国際宗教社会学会での報告を次のように述べている。
(「カルト批判への展望」『中外日報』1999年9月2日付)
つまり,イギリスのアイリーン・バーガーもマインド・コントロール論は実際には機能していないと発表したのであった。これらの海外での経験を踏まえて,桜井も実は次のような所感を表明している。
私の宗教社会学関連で言えば,『カルト』の定義,教団への入信をめぐる「マインド・コントロール論争」は殆ど不毛であり,イデオロギー対立の次元を越えな い。つまり,布教,教化における本人の自己選択と組織による影響力の度合いは,基本的に程度問題であり,個人ごと,教団ごとにケースバイケースである。100%の自由意思も,100%の強制もない(「2005年7月スペイン 国際カルト研究学会大 会参加報告」『中外日報』2005年8月23日)。
結局,カルトの定義は学者によってまちまちであり,それぞれのイデオロギーにしか基づいていないというのである。さらに,「マインド・コントロール」論に関しても,100%他人から強制されて入信することもないし,反対に100%の自由意思で入信することもないという。極めて常識的な意見に櫻井は落ち着いたのである。
こうした英米国家の傾向は,神学においても顕著に現れている。その最たるものがアメリカ系学者によるカルトの解説である。たとえば,キリスト教書籍刊行大手の教文館発行による『キリスト教神学事典』(A・リチャードソン,J・ボウデン編,1995年)である。同著の編者のひとりアラン・リチャードソンはイギリスのノッティンガム大学の穏健な神学教授であるが,リチャードソン教授が他界して後,同事典の編集を受け継いだジョン・ボウデン教授が1995年に改訂版を出している。
そこにルイス・ランボ(米カルフォルニア神学大学牧会心理学)准教授がカルトについて,「広い意味では何らかの宗教的信仰や団体を指す」としながら,具体的には「モルモンやエホバの証人」をあげ,次のようなことを書いている。
カルトと呼ばれるとしても,必ずしもすべての集団が有害な集団であるわけで はない。それはカルトであると呼ばれた集団の問題というよりも,そう呼んだ人 物の性格の問題である可能性もある。事実,カルトという言葉の用いられ方の多 様性からみて,論者の「気にいらない集団」のすべてをカルトであると定義して いるだけのことなのかも知れない(119-120頁)。
また『キリスト教神学事典』では,セクトについて「キリスト教史において,セクトとは国家と結びついた既成の教会を拒否して,個々別々に組織された信仰者のグループのこと」(402頁)と定義し,その「セクトに加入することは誰の場合であっても自発的意思に基づく決断である」(同)としている。
結語
カルト=セクト問題は,学者によって様々な解釈があり,その用語が使用される場合,使用者が誰を対象に,何の目的でその用語を使用しているのかが問われることが本稿において明らかになったのではないかと思われる。
国内では反カルト派(カルトに反対する人々)と,いわゆるカルトの人々とのせめぎ合いがあり,国際的には大陸ヨーロッパの反セクト的な姿勢とアングロサクソン系英米のような個人の自由意思を最大限に重視する,つまりマインド・コントロール論を否定する意見の相違が存在する。そのなかで,どちらの立場を支持するかは,見解の相違に過ぎない。もちろん,冒頭に触れたように殺人を容認するような場合を除いてである。
ここで改めて,ウェーバーによるセクトの定義を思い起こす。それは「自発的な信仰告白によって成員となり,宗教上・倫理上の有資各者によってのみ組織される」(『新社会学辞典』有斐閣1993年,298頁)ものであった。
ウェーバーは「自発的な信仰告白」という強い表現を使っているが,そこには神と我との一対一の厳密な関係が示されているように思われる。その関係にマインド・コントロール論のような第三者が介入することは適当でない。
もっともカトリック教会のように,神と人との間に教会が介在するとの立場もあろう。しかしここではプロテスタント的な神と人との実存的な(一対一の)関係を想定することが相応しいように思われる。
(2010年12月26日)