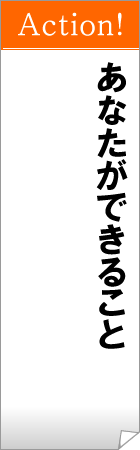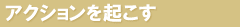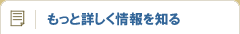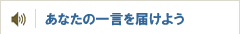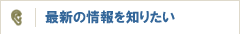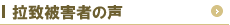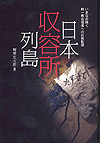新着情報
“拉致監禁”の連鎖 パートⅣ、Ⅴを読んで 宗教ジャーナリスト 室生 忠さんに聞く(上)
今利裁判は差し戻しが妥当
「拉致監禁の連鎖」パートⅣでは、今利理絵さんが拉致監禁された事件で、夫妻が提訴した民事訴訟が最高裁和解で決着する経緯を裁判資料や証言から検証した。宗教ジャーナリストの室生忠さんはパートⅣと裁判をどう見たか、批評を聞いた。(聞き手=堀本和博、岩城喜之)
一審、二審は不当判決/根絶には司法の役割重要

――「拉致監禁の連鎖」ではパートⅢまでは各ケースの拉致監禁事件の実態を追及してきたが、パートⅣでは、今利さんのケースを通して裁判所の判断が妥当だったのかどうかに重点を置いたリポートを展開した。連載を読んでの総括的な意見、批評を。
連載では、今利さんが被害に遭った事件の事実関係から裁判所がどう判断したかを分析している。裁判所も地裁、高裁、最高裁とあるが、その判決のキーポイントを非常に的確に捉えていて分かりやすく書いてある。
司法の判断を詳細に見ていくと、どうしても判決の分析が中心になってくる。そうなると読みづらい部分は出てくるが、分析は必要だ。
なぜなら、司法の判断というものは、拉致監禁問題が今後どうなるかについて大きな意味を持つものだからだ。
日本における拉致監禁問題の要素には、大きく分けて、警察・検察の態度や在り方、そしてこの問題をどう捉えるかというメディアの在り方、次に司法がどう捉えるか、この三つの柱がある。この三つの柱が是正されない限り、拉致監禁そのものも根絶できないというような構造になっている。
米国でかつて行われたディプログラミング(強制改宗)は1990年代に根絶されたが、それを最終的に実現したのは、司法、つまり裁判所の判決だった。
米国の法曹界の判断もまちまちだったが、最終的にやはり裁判所が「ディプログラミングはやってはならない」と判断して、ディプログラマーに莫大な損害賠償金の支払いを命じたことで、ディプログラミングが根絶された。
だから、司法の判断や姿勢というのは、拉致監禁を無くすために非常に大きな役割を持つ。
――最高裁が下級審の判決を問題視して、最終的に和解を勧告したことをどうみるか。
今利事件の決着を付けたのは最高裁の判断だが、私は和解では不十分だと考えている。本来、この裁判は差し戻しが妥当だ。一審、二審の判決は、まったくお話にならないものだったからだ。
この裁判は、神奈川県警宮前署が送検し、横浜地検川崎支部が起訴猶予処分にして犯罪性、違法性があるとした事件の民事訴訟だ。
刑事事件における違法性の判断と民事裁判における違法性の判断というのは、どちらが重く、より厳重に捉えられるかというと刑事の方だ。
民事裁判はもっと幅広く、その被害者の主張を十分に汲みいれて判決を下していく。これが日本における裁判の状況だ。
しかし、警察と検察が違法性の事実を認めているにもかかわらず、一審、二審でそれを真っ向から非常にドラスティックな形で否定している。このような判断の不当さは言語に絶するものがある。
――最高裁は上告棄却せずに、原告、被告の双方を呼び出して和解を勧告した。これは今利さん夫妻が下級審は不当判決だと訴えてきたことに正当性があったと考えられるか。
一審、二審における価値判断は、論理として違法行為とはっきり言わないとしても違法性、あってはならないことが行われた事実は認めた。
しかし、その行為は賠償責任を負うほどではないと判断した。
監禁という重犯罪の違法性を認めているにもかかわらず原告の主張が棄却されるのは、不当判決以外の何ものでもない。
しかも被害者たちはPTSD(心的外傷後ストレス障害)に苦しんでいる。単に違法行為があっただけではなく、後遺症を発症した。
外国の裁判においてPTSDや後遺症が残ったかは、裁判所の判断に大きなウエートを占める。
「結論ありき」のジレンマ/民事に日本特有の価値観
後遺症があるのに、賠償責任を負うほどの行為と認められないという判断はどこから出てくるのか。
最高裁の経緯を見ても、一審、二審で糾弾されるべき判断が行われたのは明らかだ。
事実関係をありのままに見て、ありのままに審理し、ありのままに判断すれば、出てくる判決というのは、あるがままの当然の判決になる。そうなっていない判決というのは、不当判決と言える。
――検察が違法性ありと判断したものを民事では重視しなかったのはなぜか。
一つには、日本の特に民事裁判における基本的な方向性、価値観が透けて見える。
それは判決文を見ても、両親らの行為は「(今利)理絵を思いやる心情」で行ったものと書いてあるように、事実関係より、そういった親の心情を極めて重視した。子は親に従うものだという価値判断が露骨に出ている。
子供の心境や内心、しかもそれは成人に達した一人の人間の内心よりも、その子供に対する親の影響力、親が何を望むのかを重視するという価値観がある。こうした価値観が表れている。
それからもう一つ、この事件の一審、二審はまず結論ありき、になっている。
その結論をどう論理的に構築して判決文にするかに懸命になったということが、連載ではっきり見えてくる。
判決文に無理が含まれるというのは、一審の裁判官も二審の裁判官も理解していたはずだろう。
客観的に判断すれば原告の訴えが認められると分かっているのに、結論としては今利さんの敗訴にしなければならない。
この矛盾に裁判所としては非常に困惑する。だから判決が延びに延びた。
現在の裁判所の在り方や方向性としては、親の立場を重視しなければいけない状況のために、論理の矛盾がどうしても出てきてしまう。最高裁への上告理由書にあるように、判決は「違法性の判断要素となり得ない要素をもって違法性がない」としたものだ。
今利裁判では、日本の裁判所が拉致監禁問題に対応するときの、裁判所が抱えるある種のジレンマが見え隠れする。
そういう意味で、連載では判決文や上告理由書の中から、キーポイントを抽出して、それをコンパクトな形で日本の裁判所の苦悩と矛盾を分かりやすく示している。
過去の記事は世界日報社ホームページでも閲覧できます。
http://www.worldtimes.co.jp/special2/ratikankin/main.html